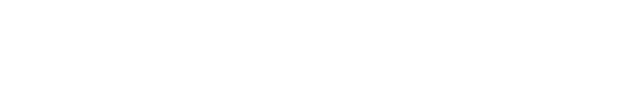発熱
発熱とは、一般にわきの下で測って37.5℃以上、あるいは平熱より体温が1℃以上高い場合をいいます。
こどもの発熱の多くは、かぜなどウイルスの感染によっておこります。ウイルスは体温が高くなると その増殖の勢いが弱まりますし、またそのウイルスを退治する防御能力は体温が高くなるとその活動が 活発になります。
こどもが元気そうで食欲もあれば解熱剤は使う必要はありません。夜、高熱で寝れない場合などは解熱剤を使用してもよいでしょう。
すぐに受診した方がいい目安としては、生後3か月未満の発熱、4日以上続く発熱、ぐったりしている、水分がとれない、顔色が悪い、嘔吐を繰り返す、苦しそうな呼吸をしている、強い腹痛、意識がもうろうとしている、けいれんなどの症状を伴う場合です。
寒そうにふるえて、手足の先が冷たく青い時は、これから熱が上がろうとしているところです。毛布などで温めてあげましょう。熱が上がりきると赤い顔をして暑そうにしはじめるので、薄着にしたり冷やしてあげたりするといいでしょう。
発熱時には胃腸の活動も低下しますので無理に食べさせることはありません。消化のよいものを与えたり、脱水症状にならないよう水分をこまめにあげましょう。